「●哲学一般・哲学者」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2333】 ピエール・デュラン 『人間マルクス』
「●文学」の インデックッスへ「●さ ジャン=ポール・サルトル」の インデックッスへ 「●講談社現代新書」の インデックッスへ
文学者の眼から見たサルトル像、小説・戯曲への手引。ボーヴォワールを嫉妬に狂わせたサルトル。
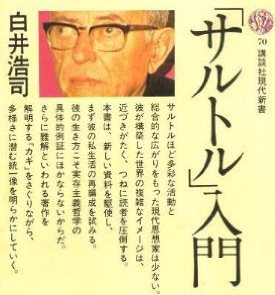

『「サルトル」入門 (1966年) (講談社現代新書)』
'07年から'08年にかけて松浪信三郎訳の『存在と無』がちくま文庫(全3冊)に収められたかと思ったら、'09年には岩波文庫で『自由への道』の刊行が始まり、こちらは全6冊に及ぶというサルトル-まだ読む人がいるのだなあという思いも。

著者の白井浩司(1917-2004)はサルトル研究の第一人者として知られたフランス文学者で、サルトルの『嘔吐』『汚れた手』などの翻訳も手掛けており、本書は、文学者・実存主義者・反戦運動の指導者など多様な活動をしたサルトルの人間像を捉えたものであるとのことですが、とりわけ、その小説や戯曲を分り易く解説しているように思いました。
サルトルとボヴォワール(来日時)
 文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。
文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。
彼は20代後半から30代前半にかけての長い修業時代に、まず、セリーヌの『夜の果ての旅』を読み、その文章に衝撃を受けて、その後いろいろな作家の作品を読み漁っていますが、カフカとフォークナーに特に共感したとのこと、また、映画を文学と同等に評価していて、カウボーイや探偵の活躍する娯楽映画も好きだったそうです(サルトルは映画狂だとボーヴォワールは書いている)。
彼の政治的な活動をも追う一方で、私生活についてもその恋愛観を含め書かれており、サルトルとボーヴォワールの2人の愛は有名ですが、サルトルはボーヴォワールと知り合った20代前半にはボーヴォワールに対してよりも年上の美女カミーユに恋をしており、また、ボーヴォワールと既に深い関係にあった30歳の頃には、3歳年下のボーヴォワールを差し置いて、12歳年下のオルガという少女に夢中になり、ボーヴォワールを嫉妬に狂わせたとのこと、そうこうしながら同時に『嘔吐』の原案も練っていたりして、ホント、精力的だなあと。
60歳の時に「プレイボーイ」誌のインタヴューに答えて、「男性とよりも、女性と一緒にいる方が好き」で、それは「奴隷でもあり共犯者でもある女性の境遇からくる、女性の感受性、優雅さ、敏感さにひかれるからで」あると答えていますが、彼の恋愛観は一般には受け入れられていないと著者は書いています。
下.jpg)
上.jpg) また、戦後も『聖ジュネ』などの文学評論の大作を発表しているものの、小説を書かなくなったのは、彼が政治に深入りしすぎたためであると書いており、この辺りは著者の見方が入っているように思えます。
また、戦後も『聖ジュネ』などの文学評論の大作を発表しているものの、小説を書かなくなったのは、彼が政治に深入りしすぎたためであると書いており、この辺りは著者の見方が入っているように思えます。
確かに、本書の冒頭には、「20億の飢えた人が地球上にいる現在、文学に専念するのは自分を欺くことだ」という'64年の記者会見での談話が紹介されてはいますが(同じ年、ノーベル文学賞を辞退している)。
本書の初版が刊行された年にサルトルは初来日していて、各地での講演会は立錐の余地もないほどの盛況だったとのこと(そういう時代だったのだなあ)、一方、ホテルについた彼が最初にやったことは、老いた母親に無事着いたことを打電することだったそうで、彼のこうした行為や壮年になっても続いた女性遍歴は、父親を早くに亡くしたこととと関係があるのではないかと、個人的には思った次第です(彼には父親の記憶が無かった)。
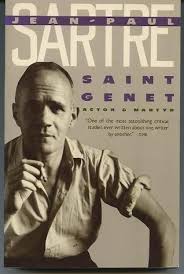


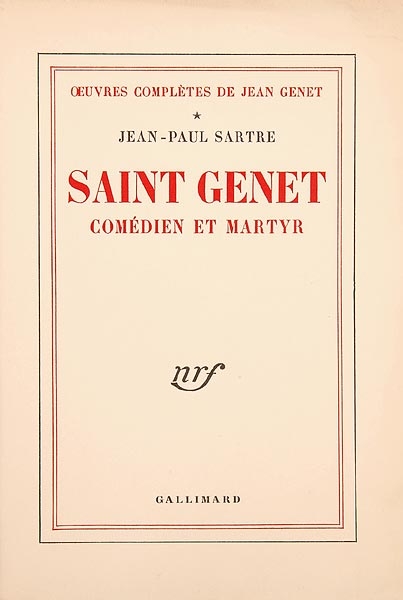

 1952年の原著発表。フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905‐1980)は、「嘔吐」「水入らず」など一連の小説でノーベル文学賞を受賞していますが(結果的には辞退)、本書は小説ではなく、泥棒から作家になったジャン・ジュネに関する哲学的な文学評伝です。
1952年の原著発表。フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905‐1980)は、「嘔吐」「水入らず」など一連の小説でノーベル文学賞を受賞していますが(結果的には辞退)、本書は小説ではなく、泥棒から作家になったジャン・ジュネに関する哲学的な文学評伝です。
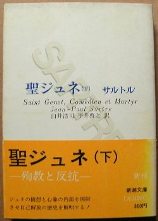 サルトルの言う「対自存在」とは、人間(意識)の在り方を指し、「それがあるところのものではない」存在として、即自存在(物)と対比されます。対自は、即自存在(事物)と一体化できず、常に自己を対象化し「無」(否定)を内包することで、「自己自身にとってある」という自由な状態であり、過去の自己から脱出し未来へ投企する(=自分を投げかける)ことで自己を形成する、「自由の刑に処せられた」存在です。 つまり、「実存」(対自存在)は、理由もなく偶然にある状況に投げ込まれて存在する無根拠な存在者であり(それはまさに我々のことを指している)、それはまた、"投企"によって自己を創出できる自由な存在者でもあって、人間はモノ(即自存在)ではないということですが、ジュネを蔑む〈まっとうな人々〉こそ、既成価値観に囚われた〈仮象〉に生き、それらを剥ぎ取ればモノ(即自存在)に過ぎないのではないかというパラドックスがここに成り立ちます。
サルトルの言う「対自存在」とは、人間(意識)の在り方を指し、「それがあるところのものではない」存在として、即自存在(物)と対比されます。対自は、即自存在(事物)と一体化できず、常に自己を対象化し「無」(否定)を内包することで、「自己自身にとってある」という自由な状態であり、過去の自己から脱出し未来へ投企する(=自分を投げかける)ことで自己を形成する、「自由の刑に処せられた」存在です。 つまり、「実存」(対自存在)は、理由もなく偶然にある状況に投げ込まれて存在する無根拠な存在者であり(それはまさに我々のことを指している)、それはまた、"投企"によって自己を創出できる自由な存在者でもあって、人間はモノ(即自存在)ではないということですが、ジュネを蔑む〈まっとうな人々〉こそ、既成価値観に囚われた〈仮象〉に生き、それらを剥ぎ取ればモノ(即自存在)に過ぎないのではないかというパラドックスがここに成り立ちます。

 (●2007年11月、ちくま学芸文庫で、サルトルの現象学的総決算とも言える主著『存在と無』(松浪信三郎:訳)が文庫化された。文庫化されたこと自体少しびっくりしたが(サルトル復活?)、20世紀を代表する哲学書が文庫で入手できるのはいいことだ。この『存在と無』を読むには相当の忍耐が必要だが、読み込めば読み込んだだけものが得られる。例えば、他者とは「眼差し」であるとサルトルは言う。つまり、他者とは「私は今、他者に見られている」という私の意識でしかない。言い換えれば、他者は私自身の意識の中にしか存在しない。私が他者の前で自由を失うのは、不本意にも、自分自身が生み出したものにすぎない「見られている姿としての自分」と自分自身を同一視させ、その結果、私の意識の自由(=「対自存在」)を凝固させてしまっているからであるという。青年期にこれを読んで、腑に落ちた思いをしたのが懐かしい)。
(●2007年11月、ちくま学芸文庫で、サルトルの現象学的総決算とも言える主著『存在と無』(松浪信三郎:訳)が文庫化された。文庫化されたこと自体少しびっくりしたが(サルトル復活?)、20世紀を代表する哲学書が文庫で入手できるのはいいことだ。この『存在と無』を読むには相当の忍耐が必要だが、読み込めば読み込んだだけものが得られる。例えば、他者とは「眼差し」であるとサルトルは言う。つまり、他者とは「私は今、他者に見られている」という私の意識でしかない。言い換えれば、他者は私自身の意識の中にしか存在しない。私が他者の前で自由を失うのは、不本意にも、自分自身が生み出したものにすぎない「見られている姿としての自分」と自分自身を同一視させ、その結果、私の意識の自由(=「対自存在」)を凝固させてしまっているからであるという。青年期にこれを読んで、腑に落ちた思いをしたのが懐かしい)。
